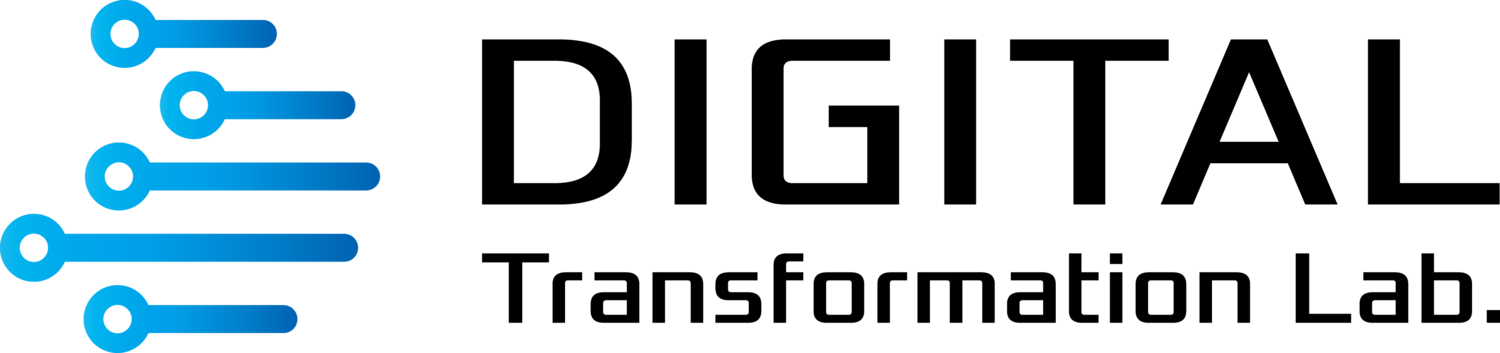DXの定義の改訂
2022年2月、エリック・ストルターマン教授は、DXを推進する日本の様々な組織の現状を考慮して、社会、公共、民間の3つのレベルで、デジタルトランスフォーメーションの定義を以下の通り再策定しました。本定義にあたっては、日本の社会と企業の競争力と成功を高めることをビジョンとして掲げる株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所とコラボレーションの上、策定を進めました。
背景・目的
2004年、エリックストルターマン氏(当時ウメオ大学教授、現在インディアナ大学副学部長兼株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所エグゼクティブアドバイザー)が提唱したDX(デジタルトランスフォーメーション)においては、情報技術の継続的な発展は、新たな非常に複雑な環境を生み出し、人々の生活も劇的な影響を受けることから、革新的に進化する技術の経験的・理論的な理解を前提に、美的体験のもたらす価値をメソトロジーの中心的コンセプトに位置づけることを求めるものでした。しかしながら、特に日本においては、その複雑なコンセプトは要約され、様々に解釈されています。
当初のエリックによるDXの捉え方は以下のようなものでした。
「The digital transformation can be understood as the changes that the digital technology causes or influences in all aspects of human life.
人々の生活のあらゆる側面に、デジタル技術が引き起こしたり、影響を与える変化のこと(弊社訳)」
- デジタルトランスフォーメーション(DX)とは〜提唱者の定義(2004年当時)を振り返る
その後、エリックによるDXのコンセプトをベースに、日本では今まさにDXブームへ発展しています。その一方、様々な組織が独自に解釈、公表するなど、当初エリックが発表したコンセプトと異なる使われ方が実態として増えております。
例えば、エリックは、DXをデジタル技術による外部環境の変化と捉え、それが人々の生活のあらゆる面に影響を与えると提唱しました。エリックは明確に、当初の論文において、盲目的にデジタル技術を受け入れることに批判的な立場をとっていますが、日本においてはより良い影響があると訳され、解釈されています。また現在では、DXは組織や個人が主体的かつ戦略的に起こすものとしての使い方が主流となり、特に企業、行政、自治体などの自己変革という面で使われている他、単なるデジタル化として使われているケースも増えています。
これらの日本の実態を考慮し、エリックは、株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所の支援を元に、新たなDXの定義を策定いたしました。2004年当初の定義は社会におけるDXを表していましたが、DXは組織や個人が主体的かつ戦略的に起こすものという使い方をサポートする形で、今回の定義の策定に反映させ、社会、公共、民間の3種類の用途別に策定いたしました。
-
デジタルトランスフォーメーション(DX)は、人々の生活のあらゆる側面に影響を及ぼす。DXは単なる技術的な発展ではなく、社会を構成する私たちが、リアル空間とデジタル空間が融合し高度に複雑で変化する世界にどのように関わり、接するかに影響を与える広く深い変化である。DXはよりスマートな社会と、一人ひとりが健康で文化的なより良い生活を送れるサステナブルな未来の実現をもたらしうる。
Digital Transformation (DX) influences all aspects of human life. DX is not solely a technical development, it is a broad and deep change merging the real and digital space in a way that influences how we as a society approach and deal with a highly complex and changing world. DX has the potential to improve and lead to standards of wholesome and cultured living and a sustainable future with a smarter society and a good life for each individual.
-
デジタルトランスフォーメーション(DX)は、あらゆる組織や分野でスマートな行政サービスを展開し、革新的な価値創造を支援することができるものである。また、DXは住民をより安全・安心にし、快適で持続可能な社会へと導くことができるソリューションを生み出すことで、住民の幸せや豊かさ、情熱を実現し、地域やエリアの価値を向上させることを可能にする。DXは既存の仕組みや手続きへの挑戦、より住民本位の革新的な解決策を協働で考えることを促す。DXを推進するためには、組織のあり方や文化を革新的、アジャイル、協調的に変革することが必要である。DXは、トップマネジメントが主導して行うものでありながら、全てのステークホルダーが変革に参加することを求められる。
Digital Transformation (DX) makes it possible to develop smart government services in every organization and category and to assist innovative value creation. DX also makes it possible to improve the value of areas and regions by enabling happier, richer, and more passionate conditions for residents by creating solutions that can make residents more safe and secure and lead to a comfortable and sustainable society. DX encourages everyone to challenge existing structures and procedures and in a collaborative way think about innovative solutions that are more resident-oriented. DX requires transforming the attitude and culture of the public sector to become innovative, agile, and collaborative. DX requires all stakeholders to participate in the transformation while being initiated and led by top management.
-
デジタルトランスフォーメーション(DX)は、企業がビジネスの目標やビジョンの達成にむけて、その価値、製品、サービスの提供の仕組を変革することである。DXは顧客により高い価値を提供することを通じて、企業全体の価値を向上させることも可能にする。DXは戦略、組織行動、組織構造、組織文化、教育、ガバナンス、手順など、組織のあらゆる要素を変革し、デジタル技術の活用に基づく最適なエコシステムを構築することが必要である。DXは、トップマネジメントが主導し、リードしながら、全従業員が変革に参加することが必要である。
Digital Transformation (DX) can empower industries to transform the delivery of their value, products, and services, to accomplish their business goals and visions. DX also makes it possible to improve the overall value of a company in the industry by changing the delivery method to offer a higher value to their customers. DX requires organizations in the industry to redesign all elements of the organization, including strategy, organizational behavior, organizational structure, organizational culture, education, governance, and procedures to create an optimized ecosystem based on the use of digital technology. DX requires all employees to participate in the transformation while being initiated and led by top management.
DXを定義から学びなおすために最適な「1冊目に読みたいDXの教科書」
1冊目に読みたいDXの教科書について
出版に関して
書籍出版関連ブログ
DX入門書を執筆して書籍のDXに挑戦
DXの教科書を執筆することになった経緯についてご紹介いたします
DXの教科書を執筆したツールについてご紹介いたします
DXの教科書を執筆したプロセスについてご紹介いたします
DXの教科書の見本誌を手に取った喜びについて共有いたします
書籍のDXと「1冊目に読みたいDXの教科書」のデジタル特典の解説
書籍のDX(デジタル化)の要素と照らし合わせて、本書で実施したデジタルの工夫について共有いたします。
DX実践者のクローズなコミュニティで情報を蓄積することにより、メンバーの実践力を高めます。
DX実践道場 https://dojo.dxlab.jp/
DX経験者や専門家の実践知を集積するオンラインスクール
DXラボ通信 https://www.dxlab.jp/press
最新の実践的DX情報の発信しているブログ
定義の引用・転載について
本定義は日本の社会の競争力を高めることを目的として、策定・ご提供しています。出典を明記した上での引用・転載を推奨いたします。
いますぐお問い合わせ
デジタルトランスフォーメーションを通じて日本企業の競争力を飛躍的に高め豊かな日本を後世に引き継ぐをビジョンとする当社へお任せください。
まずは、意見交換からでも結構です。皆様の組織の明日のためにいま何をすべきか一緒に考えられればと存じます。